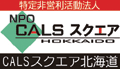2007年11月12日
建ブロの日【11月18日 土木の日を考える】
まず始めに、「11月18日」がどうして「土木の日」になったのか書いてみたいと思います。
土木の2文字を分解すると十一と十八になることと、土木学会の前身である「工学会」の創立が明治12年(1879)11月18日であることから、1987年11月に土木学会が11月18日を「土木の日」と制定しました。
土木が国家財政の敵のように言われている今日この頃ですが、確かにそう言う部分もあるでしょう。
バブルが終わり経済が低迷した時、公共需要に財政をつぎ込んで経済立て直しを図ろうとした事実もありますので、私はあえて否定はしません。
土木不要論を唱える人もいれば、そうでない人も居て、色んな考えの人がいて世の中バランスが取れるのだと思います。
私は、土木業界で仕事をしている訳ですが、一口に土木と言って色々な分野があります。
都市計画・河川・砂防・海岸・港湾・空港・電力・道路・鉄道・トンネル・農業・水産・森林・上下水道など、色々な分野に分けることが出来ます。
そして、私たちが普段生活する環境は、ほとんど全て土木によって成り立っていると言っても過言ではありません。
その中でも私は農業土木に一番長く携わってきたので、農業土木について書いてみたいと思います。
特に、私は北海道に住んでるので、北海道のことを書きます。
農業土木と言っても、ピンと来る方はそう多くはないかも知れません。
たとえば、農道・用水路・排水路・パイプライン・ダム・頭首工・基盤整備などがあります。
北海道開拓の歴史は明治6年(1873年)に屯田兵により始まりました。
それ以来130年以上の間、現在も農業のための整備が行われています。
水田を例にすると、
水田は水が必要です。
水田に水を引くためには用水路が必要です。
用水路に水を流すためには、頭首工やダムが必要です。
さて、水田に水を引くだけで良いのでしょうか。
水田に入れた水は排水しなければなりません。
表面水も、そして浸透水も排水する必要があります。
そのために、排水路、そして暗渠排水路も整備しなければなりません。
忘れてならないのは、土作りです。
水田が玉石ゴロゴロしていたり、土が固かったり、粘土質土壌で水はけが悪くてはうまく耕作できません
そのため、玉石の除去、心土破砕、客土などの土壌改良も必要です。
北海道で今のようにお米が取れるようになったのは、水稲の品種改良だけではないはずです。
上記のような水田の整備があって始めて、おいしい北海道米が取れるようになったのだと思います。
現在北海道が、日本の穀倉地帯として食糧基地と成り得たのは、土木は無駄だとか不要だとか言われていても、こういった農業土木による農地の整備が脈々と行われてきたからではないでしょうか。
11月18日は土木の日です。
たまには、土木ということを生活に関わる部分から考えて見るのも悪く無いんじゃないかと、私はそう思っています。
トラックバックURL
トラックバック一覧
1. 建ブロの日【11月18日 土木の日を考える】 [ CIC建設コラム ] 2007年11月13日 08:37
昨日は、5回目の建ブロ(建設ブロガー)の日。お題は、「11月18日 土木の日を考える」でした。 一般的には